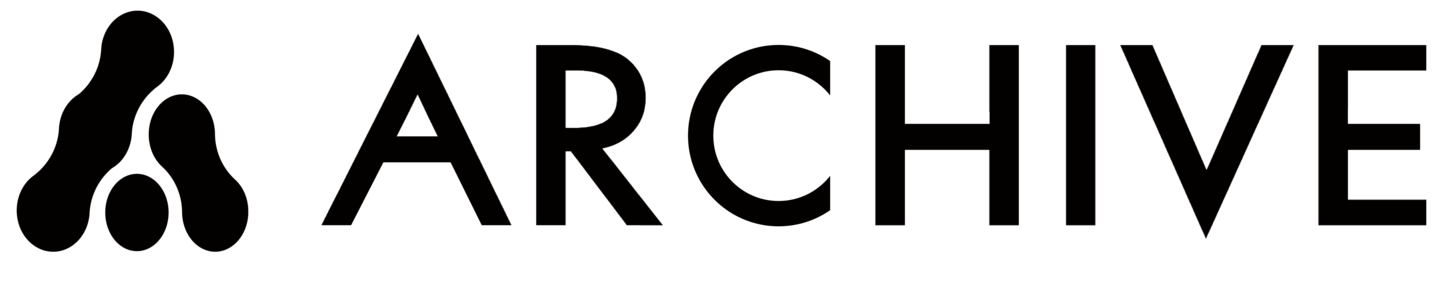海辺の生の神秘
海の周縁は不思議な、また美しい場所である。地球の長い歴史をつうじて、ここは波が猛烈に陸地にぶつかっては砕け、潮が陸地にのしかかっては前進し、後退し、また押し寄せる絶えざる動揺の場所であった。岸と水との接する線がまったく同じ状態でいることは二日とない。今日は陸地が少々多く海に食われるかもしれないが、明日はそれが少々少ないかもしれない。海の周辺はいつも捕まえどころがなく、確定できない境界線をなしている。
こんなふうに変わりやすいところに生きていることのできる生物は適応力をもった最も強い生物だけである。といっても干満潮線のあいだのこの場所には、植物や動物が目白押しの状態である。生きることがいかにも難しいこの世界にも、生物は考えられるかぎりのほとんどあらゆる場所を占めて、恐るべきたくましさと生活力とを示している。生物は干満潮線の間の岩石の上を 絨毯 のようにおおっていて、割れ目や隙間のなかに入り込んでいるかと思えば丸石の下にも潜んでおり、海の洞穴の濡れた薄暗いところにも人目を避けて住んでいる。ちょっと見ただけでは生物なんかいそうもないようなところにも、生物は深く砂の底や、穴の隠れ家や管や通路のなかにひそんでいる。固い岩にトンネルをつくり、泥炭や粘土に穴を開けて食い入っている。海草や、あるいは漂う舟の円材や、エビの固いキチン質の殻などについて、これをおおっている。非常に微細なものは岩石の表面を薄い膜のようにおおう。バクテリアから、砂粒の間の暗い水たまりのなかを泳ぎ回っている小さな生物までもある。
砂の下の世界
一粒一粒の砂にはそれぞれ毛管引力で薄い水の膜がついているので、打ち寄せる激しい磯波の力が働いても、砂の一粒一粒が互いにこすれ合うようなことはない。この小さな世界のなかに、考えられないほど小さな生物が砂の一粒の周りの水の膜の中を泳ぎ回っているが、それは地球の球面に広がる大海の中を魚が泳ぎ回るような具合である。この毛管水のなかにいる動物には単細胞動物、ミズダニ類、エビのような甲殻類、昆虫類をはじめ非常に小さな各種の虫の幼虫があり、これがみんな人間の感覚ではその尺度を理解することもできないような非常に小さな世界のなかで、生活したり死んだり、泳いだり食べたり、呼吸し生殖したりしている。
砂のなかにはもっと大きな生物もたくさん住んでいる。潮の満ち引きによって隠れたり現われたりする広い平らな浅瀬の上を横切って行くとき、私はいつも地下の都市の薄い屋根の上を踏みしめているんだなと思わないではいられなかった。もっとも、この都市の住民の姿はまったく見られないか、あるいはほとんど見られなかったが、地下の住まいの煙突もあれば通気管もあったし、いろいろの通路や往来が真っ暗な底に通じていた。小さなゴミの山がまるでなにか都市の清掃でも行われているかのように、そこここにおかれていた。それでも住民の姿は見かけなかった。彼らは暗い測り知れない世界のなかにひっそりと暮らしているのである。
スナモグリ
穴に住んでいる動物都市の住民のうちで一番数の多いのはスナモグリであった。これは長いほっそりした体をした奇妙な格好の動物で、ほとんど外へ出歩くことをしない。したがって普通のエビのように体を保護する固い外骨格を付ける必要がない。その代わりに自由自在に曲がる外皮に包まれているが、この外皮なら狭いトンネルのなかで砂を掘ったり体の向きを変えたりしなければならないスナモグリには都合がよい。体の下側には平たい付属肢が数対あって、これを働かせて海水が絶えず穴のなかを流れて通るようにしているが、これは深い砂の底では酸素の供給が不十分なので空気にさらされた海水を上のほうから引き込んでやらなければならないからである。潮が上げてくるとスナモグリは穴の口まで上がっていって砂粒をふるいにかける仕事を始める。そしてバクテリア、顕微鏡でなければ見えないような単細胞の珪藻植物、あるいはそれよりも少し大きい有機質破片の粒子など選り分ける。
スナモグリの穴は平らな干潟のいたるところに散在していて、その入口の直径は鉛筆の直径よりもかなり小さく、ふんの小さな球が小高く盛り上がって、その入口を囲んでいた。この小さな球がこんなにたくさんたまるのは、スナモグリの生活法からきている。スナモグリは砂や泥のように消化できない物にまざっている食物をとるので、砂や泥を非常に大量に食べなければならないからである。この穴こそは一つ一つ、砂のなかに一メートルないしそれ以上も延びている穴の住まいへとつづくもので、この入口がその目印になる。穴の住まいは垂直に近い長い通路になっていて、それからいくつものトンネルが枝分かれしている。トンネルはこのエビの都市の暗い湿った基底部に通ずるものもあれば、表面に通じていて非常口の役目をしているのではないかと思われるものもある。この穴の住まいの 主 たちは、私が一計を案じて一度に二、三粒ずつ砂をその門口から中に落としてやるまでは姿を見せなかった。
海産多毛類
同じ平らな干潟のもっと泥地になったところにはタマシキゴカイが住んでる。それは低い火山のような円錐形をした円形の黒い屋根があるのですぐ分かる。ヨーロッパでもアメリカでもタマシキゴカイのいる海岸では、タマシキゴカイが大変な努力をして浜辺を変化させ更新させて分解中の有機物の量を適当な釣り合いに保っている。これがたくさんいるところでは、一年間に一町歩につき四千八百トンもの泥土を片づけてしまう。広々とした平らな砂地にはタマシキゴカイをはじめ他の海産多毛類が絶えず穴を掘っている。その一つであるウミイサゴムシは自分の食べ物のまざっている砂を使って円錐状の管をつくり上げ、軟らかい体を保護してトンネル掘りに都合のよいようにする。これが生きて活動しているところを見かけることもときどきあるが、潮が引いた後にたまった破片物のなかにこの管の 空 になったのを見かけることのほうが多い。この管は見かけは脆そうだが、これをつくった大工が死んだあともいつまでも壊れないでいる。これこそ砂の天然のモザイクで、砂が一粒並んだだけの厚さで、組み立てた石はまことに細心の注意を払って互いにはめ込まれ、接着されているのである。
モール・クラブ(日本のスナホリガニの仲間)
岸と水の接する地帯を利用してうまく生活しているもう一つの生物は、スナホリガニである。これは波の砕けるところで漁をする生物で、網を非常に能率的に使って水中に漂う微生物まで捕まえてしまう。このカニが餌にありつこうとするときは、濡れた砂のなかに体をもぐり込ませて、口のあたりと、羽毛の生えた長くねじ曲がった触角だけを砂の外に出している。そして波が押し寄せてくるときは餌をとろうとしないで、波が浜に当たって勢いが弱まり、沖に向かって引いてゆくときまで待っている。勢いを失った波が低くなって三、四センチの水深になったところで、スナホリガニにはその流れのなかに触角を突き出す。そして、しばらくの間「漁」をすると、口の周りを囲んだ付属肢の間を通して触角をひっこめる。こうして、捕まえた餌を取り込むのである。
スナホリガニの都市では全住民が波の砕けるあたりに住んでいる。上げ潮になると岸近くに来、引き潮になると沖へと引き退がる。潮が上げてくるにつれて、そっくり 一床 のスナホリガニが揃って何回も場所を変えるが、そのたびにさらに岸近くへ寄って穴を掘る。
スナホリガニに大集落があるところをたまたま歩くと、この「砂地がもぞもぞと生き返える」のを見ることができるが、これはまことに目覚ましい光景である。一瞬砂地には生物が全然いないように見えるが、引き潮の水が液体のガラスの薄い流れのようになって沖へ去ろうとするその一瞬に、突然何百とも知れない地の精のような奇怪な小さな顔が、その砂地のなかからのぞく。小さくてぎょろっとした丸い目玉と長いひげを生やした顔が、あまりに背景の色と似かよっているのでほとんど目につかない色の体にくっついている。さらに、ほんの一瞬のうちにその顔がぼやけて見えなくなってしまうと、目のくらましようがあまりに激しいので、いままで見たことがまったくの空想であったのかと思うほどである。動いて止まない砂と泡だつ海水がつくるこの魔法のような世界が織りなした幻影に過ぎなかったのか、と思うほどである。
スナガニ
スナガニ(日本では相模湾以西にいる)の住んでいる海浜はどこでも穴の主の習性にしたがってスナガニの穴が毎日、また季節的にリズムをなして現われたり消えたりする。夜スナガニが浜辺に餌をあさりに出たときは、穴住まいの口はあけっぱなしになっている。そして明け方近くになってもどってくるが、原則として各々のスナガニがいままで入っていた穴にもどるのか、あるいはただ単に手近かな穴にもどるだけなのか、まだはっきり分かっていない。
そのトンネルはたいてい簡単な竪穴が一本通っているだけで、砂のなかに約四十五度の角度で掘り下げられており、そのどんづまりは広がった洞穴になっている。この洞穴から砂の表面に上がっている補助の竪穴を一本持っているスナガニにもわずかだがいる。これは非常の場合に役に立つ。おそらく自分より大きなカニが襲いかかってきて正面の竪穴から降りてきたときに使うのだろう。
スナガニは朝早く、その日の穴と決めた穴を直したり、拡げたり改良工事をしたりする。穴から砂を選び上げるときはいつでも横歩きで出てくるが、運んでくる荷物の砂はこの歩き方で後のほうになった側の脚の下に包みのように抱えている。ときには穴の住まいの口までくるやいなや、非常な勢いで砂をはねとばしておいて、すばやく穴のなかにとび込むこともあり、またときには穴の口から少し離れたところまで運んで行ってそこに置くこともある。スナガニにはその穴の住まいに食物をまずたくわえておいてから自分もそのなかにひっこむこともよくある。正午ごろになるとほとんどすべてのスナガニがトンネルの入口に戸を立ててしまう。
海浜の穴は夏中ずっと毎日こんな要領で出現するのである。秋になると、たいていのスナガニが満潮でも潮が届かない浜辺の乾いたところに移ってしまう。その穴は夏よりも深く砂のなかに掘り下げられるが、それはちょうど穴の主たちがその季節の寒さを感じているかのようである。そして、それからあとは、ちょっと見たところでは、この砂の戸は閉めっきりらしく、春まで開けられないようだ。
冬の浜辺にはスナガニのいる気配も穴のあるらしい様子もない。一・八センチくらいの子供のスナガニから成長しきった大人のスナガニにまで、すっかり姿を消してしまっている。おそらく冬眠で長い眠りに落ちているのだろう。ところが、陽ざしの暖かな春の日に辺を歩いてみると、そこここに穴の住まいの口が開いているのが見られる。そして、たちまち一匹のスナガニが一目でそれと分かるピカピカした新調のスプリング・コートを着けて戸口に現われる。そしていかにも試しにやってみるのだと言わんばかりに、春の陽を浴びてひじを延ばしながらそり返える。空気のなかにまだ寒さの気配が漂っているようだと、スナガニはすぐ穴に引っ込んで戸を閉めてしまう。しかしやがて季節はめぐってゆき、広々としたこの浜辺の上のほうではスナガニがあちこちで眠りから覚めかかってくる。
テングニシの仲間
どんなに浅くても、とにかく水引き潮の洲の上にかぶさっているところでは、生物がその隠れ家からはい出してくる。私がジャブジャブ歩いて渡ると、若いカブトガニが一匹あわてて出てきて、もっと深いところへ身をひそめる。トード・フィッシュといってカジカに似た魚(アメリカ大西洋岸産)の小さなやつが群生したアジモ(藻)の茂みにもぐりながら、私の足もとでブツクサと文句を言うのが聞こえるが、それはまるで彼の世界に踏み込んだ見慣れぬ訪問者を非難しているかのようである。貝殻の周りにきちんとした黒いらせんがついていて、それにふさわしく脚まで黒い巻貝が、大急ぎで水底をはって逃げる。そのあとにははっきりと足跡が砂の上に残る。潮が引いてしまうと、あちこちに大きなテングニシの仲間の貝がはいまわって、餌を求めているのが見られる。その餌は砂のなかにひそんでいる二枚貝である。テングニシは味覚が鋭いので、それを頼りに、二枚貝の排水管から出る水の、目には見えない流れにたどりつくのである。こうした味覚の道をたどってゆくと太ったレザー・クラムというマテガイのような二枚貝のところまで行きつくこともあるだろうが、この貝は貝殻から体がはみ出して貝に包まれている部分は少ない。あるいはまた、二枚の貝殻にしっかり体を閉ざしたビノスガイの仲間に行き当たるかもしれないが、ビノスガイの仲間でさえテングニシにかかってはやられてしまう。
ところが生物界の循環作用──つまり、ある種の生物が他の種の生物に依存しているという複雑な関係──はこれでおしまいになったわけではない。海底の暗い小さな穴のなかにテングニシの敵がひそんでいる。それはスベスベオオギガニ(日本では伊勢湾から南にかけている)で、大きな紫色の体をしており、その鮮やかな色をしたはさみは何物を砕いてしまうような勢いでテングニシの貝殻を少しずつ破り去ってしまう。このカニは突堤の石のあいだの洞穴に、あるいは貝殻質の岩が浸食されてできた穴に、ひそんでいる。スベスベオオギガニの住家のあたりには、まるで物語に伝えられている巨人の住家もかくやと思われるように、餌食にされたものの遺体がバラバラになって転がっている。
テングニシがこの敵から逃げおうせたとしても、もう一つ空からくる敵がいる。カモメが大挙して波打際にやってくることだ。カモメはその餌食の殻を砕くような大きなはさみなどはもっていないが、先祖伝来の知恵で殻を砕く別の方法を学びとった。干潟に姿を現わしているテングニシを見つけると、カモメはそれをつかんで空高く舞い上がる。そして舗装道路や突堤を探すか、あるいはただの岸辺でも見つけて、その上に高く舞い上がって餌食を落とす。そして、すぐそのまま餌食のあとを追って地面まで舞い下り、粉々に砕けた貝殻のなかから貴重な珍味を拾い集めるというわけである。
どこの海岸に行っても過去と未来がこだましている。それは時の流れ、海の永遠のリズム──満ち引きする潮、打ち寄せては砕ける磯波、川のような勢いで押し寄せる海流など──のこだまに閉ざされて、形づくられ、移り変わり、容赦なく流されてゆく。海が新しい海岸線をつくり出すごとに、いろいろな生物の群がそこに向かって波のように押し寄せてきて、新しい足場をつくる。そこで初めて、生命というものは海にある物理的な実在物のどれにも劣らず実体的な力であることがわれわれに分かってくる。その力は強くて、ある目的を持っており、それをくじいたり、その目的から逸らさせたりしてしまうことは、満ちてくる潮を止めることができないのと同じように不可能なことである。